| | リフォームのすすめ | 外壁塗替えの話 | 住まいの健康診断 | 作品集 | お問い合わせ| | 会社案内 | 商品情報 | 住まいの相談会場 | GARDEN | リンク | プライバシーポリシー |
〜 耐震補強の話 Part2 〜
| ■ マンションなどの中高層建築物は! 一般的に柳のように揺れて衝撃を吸収するため地震には強いとされるが、ある専門家は「長い年月がたてばコンクリートも劣化し、鉄筋も錆びる。高い技術が結集している超高層ビルならともかく、古い雑居ビルや賃貸マンションなどは、耐震基準を長年保持しているのかということが問題だ。」と語る。 ビルの耐震診断をする業者も多数あるが、発注主は官公庁や企業、学校などがほとんど。 あるゼネコン担当者は、「見積もりまで行っても住民の合意が得られないなど、マンションで耐震補強をケースは皆無に近い。危険とされる81年以前のマンションやビルも相当残っている」と警鐘を鳴らす。 また、「耐震性については法律上、説明の義務がない。業者の積極的な説明も必要だし、消費者も車やオーディオを選ぶ時のように問題意識を持って徹底的に選んでほしい」 |
| ■ 阪神淡路大震災の教訓を今に! |
||||||||||||||||||||||||
| 平成7年1月17日、阪神・淡路大震災は、近年に見られない非常に大きな地震であり、関東大震災後に初めて経験する大都市での大規模地震でした。 この地震による死者の84%が住宅などの建物倒壊を原因とする窒息死や圧死です。 戦後最大の惨事から導き出される最大の教訓は住宅の「耐震化」なのです。 |
||||||||||||||||||||||||
表-1 阪神の地震被害(建築時期と被害状況:三宮地区)
|
 |
 |
 |
| ■ 新耐震基準(新耐震設計法)とは? わが国の現行の耐震規定は1981年(昭和56年)に出来たものでそれを境に建物の強度に差が出ています。旧基準は、1923年9月1日の関東大震災で誕生し、新潟地震(1964年)、十勝沖地震(1968年)、宮城県沖地震(1978年)などにより部分的な改正が行なわれましたが、基本的な変更がなく時代にそぐわないものとなりました。そのため、旧耐震基準の見直しが必要になったわけです。 |
| ■ 新耐震基準(新耐震設計法)の目標 皆さんは、地震に対して全く被害がない設計が現在の耐震基準だと思う人がいると思います。しかしながら現行の耐震基準は地震時にどの程度の能力を持たせているかを定めていて、建物に被害が起こらない基準ではないこと。様は、目安を設けていることです。 建物の多くは大地震を経験せずに一生を送ります。100年に一度の災害に耐えるように設計することは、経済性を大きく損ねることになり、一般住宅では現実味が薄いでしょう。そこでどの程度の耐震能力をもたせるかが、いまの基準なわけです。その内容は |
| 中地震 (震度5程度 80〜100ガル) |
大地震 (震度6程度 300〜400ガル) |
|
| 構造体 | 大きなひび割れは起こらない | 部材が損傷しても倒壊しない |
| 非構造体 | 外装の損傷はあっても軽微 | 外装、設備等に損傷が出る |
| 再使用 | 補修が必要でも軽微な補修で再使用可 | 再使用には、慎重な調査が必要 |
| つまり、建物は、中程度の地震に対してほとんど被害を生じず機能を維持し、大地震に対して部分的な被害があっても人名に被害を生じないようにする(倒壊を防ぎ圧死者を出さない)、ということです。 |
市川市のリフォーム・船橋市のリフォーム エコライフTOP
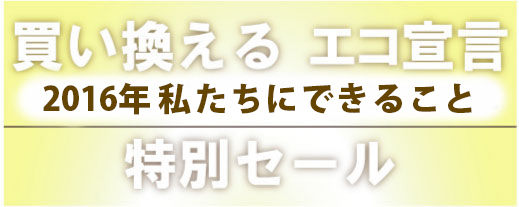 |
■CONTENTS■
| リフォームのススメ |
| 耐震補強の話 |
| 外壁塗替の話し |
| 住まいの健康診断 |
| 商品情報 |
| 作品集 |
| GARDEN |
| リンク集 |
| お問合せ |
| 会社案内 |
| スタッフ大募集 |
| SITEMAP |
| 【営業エリア】 |
| 東京都23区 江戸川区、葛飾区、江東区、墨田区、台東区、、足立区、荒川区、千代田区、港区、品川区、大田区、新宿区、中央区、渋谷区、練馬区、世田谷区、杉並区、中野区、北区板橋区、豊島区、目黒区、 千葉県内 市川市、船橋市、浦安市、鎌ケ谷市、松戸市、千葉市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、流山市、八街市、白井市 埼玉県内 さいたま市 大宮区 中央区 西区 北区 見沼区 桜区 浦和区 南区 緑区 岩槻区 川口市 三郷市 八潮市 草加市 蕨市 鳩ヶ谷市 越谷市 戸田市 入間市 |


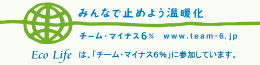
| 船橋市南海神1-1-3 tel:047-435-2345 fax:047-435-2332 |